羨道入り口には巨石が転がっています。

この石室は珍しいのでリンクなしで無理から紹介。↓
じゃ〜ん!
でこれがその石室です。
終末期に渡来系の墓として流行した形状だと言われています。

命知らずのアナタのために↑この写真も拡大できます!
しかも相当豪快に重いです。
でも一見の価値アリ!( ̄ー ̄)=3 ガンバ♪
さてこの磚積ですが「磚(せん)」とは6世紀ごろ百済から渡来した
「タイル」のような焼物を意味します。
それが後々瓦や敷物、壁に変化していきました。
石室には焼物でなく→
横にして
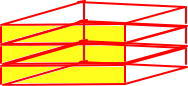 積まれています。
積まれています。石室内で見えている石の部分はごく一部(黄色い部分)
掘り返すと、巨大な石で作った石室と同じくらいの
厚みがある石の層が出てきます。
高さを得るためにたくさん石が要りますが、巨石を運ばなくていいし、
墳丘を面で支えているので強度もあるんですね。
ただ、カヅマヤマ古墳に見られた崩壊跡ように
横から押されるような地すべりには弱いと思います。
地震や雨の多い日本で長続きしなかったのはそのせいかな。
そして、石室の中には組み合わせ式の箱型石棺が。
調査前にはバラバラになっていたものの
石の破損もなく、そのまま復元・安置されています。

もちろん、でかくなって↑臨死体験可能!(←は?)
戻る 次へ